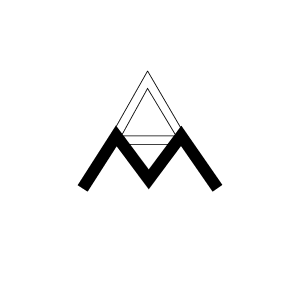滋賀県大津市・京都市で耐震診断依頼なら合同会社 前畑建築事務所
1.耐震診断とは

耐震診断とは建物の健康診断とお考え下さい。 地震が起きた際にその建物が安全か判断する診断を行います。 診断の結果で補強などが必要な場合は補強を計画し検討します。 1981年以前に建てられた建物(旧耐震基準)やバランスが悪い建物、大人数が居住している 建物等の建物は積極的に耐震診断を受けられることをお勧め致します。 *阪神淡路大震災において1981年以降の新耐震基準で建てられた建物は比較的被害が少なかったと言われています。
2.耐震診断実施義務
1981年以降の新耐震基準以前に建てられた病院やデパートなどの大型施設に耐震診断を義務付ける改正耐震改修促進法が平成25年6月可決、成立しました。 地方自治体による診断結果の公表や、建物が耐震基準に適合していることを示すマークの新設も盛り込んでいます。 耐震診断期限は2015年末で、耐震診断の対象は政令で定めるられる。 国交省はデパートや病院は延べ床面積5千平方メートル以上とし、避難が困難な児童や高齢者が利用する施設はより小さいものも含まれる事になります。 滋賀県で耐震診断義務付け対象建築物はこちら
3.耐震診断の流れ
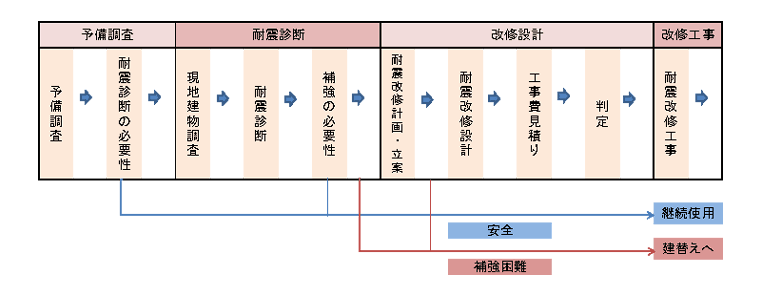
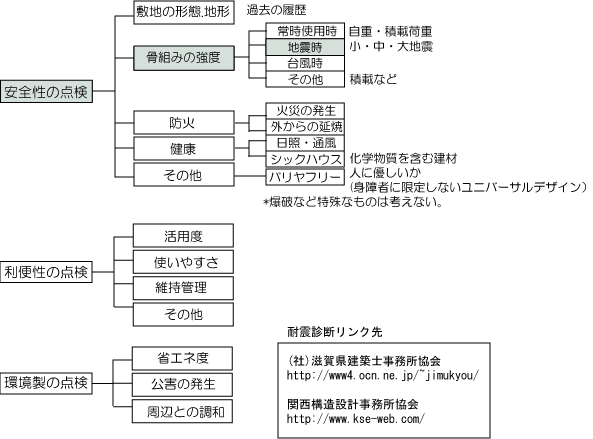
1.予備調査 ご依頼の建物の図面のみで調査致します。 診断に必要な情報を取集します 2.耐震診断の必要性 耐震診断には1次診断・2次診断・3次診断の3つの診断方法があります。 1次診断(簡易診断)で異常があった場合2次診断・3次診断を行うことになります。 3.耐震性能を判断する 耐震診断の結果を受けて、建物を建て替えするか補強するか判断致します。 4.耐震補強設計 耐震補強の必要性が高いものについて詳細な情報に基づき、補強の必要性の最終的な診断をし、補強方法の選定及び補強効果の確認を行うことを目的としています。
4.日本における建物の耐震化の状況

国道交通省が発表した日本の耐震化の進捗状況は、平成20年時点で住宅が約79%、多数の者が利用する建築物が80%となっています。 また、政府は「新成長戦略」、「住生活基本計画」において、住宅の耐震化率を令和2年までに95%に、令和7年までに耐震性を有しない住宅のストックの「おおむね解消」を掲げています。
5.耐震診断を誰に頼むか?
一般的な住宅を耐震診断する場合、資格要件はありません。一応「耐震診断士」という資格のがありますが、これは国家資格ではないので、診断をするにあたり必須ではないのです。(学校や商業施設など、耐震診断を義務付けている建物の耐震診断は、建築士資格が必須) しかし、耐震診断をできるだけの豊富な知識と経験がある建築士の資格者に依頼するほうが安心です。 なぜなら耐震診断の後の耐震設計は建築士の仕事となり、耐震基準適合証明書を発行できるのも建築士のみです、 尚、助成金を受けたい場合には自治体に登録された建築士の耐震診断を受ける必要があります。 そんな建築士の中でも「構造設計」「意匠設計」「設備設計」が得意な建築士事務所があり、耐震診断において「構造設計」について詳しいことが一番大事となってきますので、「構造設計」を得意とする建築士事務所に依頼することをおすすめします。 当社は「構造設計」を得意としており、耐震改修工事のことも良く理解しております。
6.耐震診断に使用する図面がない場合
設計図面がなければ、設計図面を復元するしかありません。 耐震診断は、基本的に設計図面をベースにして実施します。 耐震診断を設計図面がないまま進めるのは、大きな障壁になる可能性があるからです。 ただ、耐震診断には図面が必要なので図面がある場合に比べて高くつきます。 図面を製作する費用として別途費用がかかります。 これは建物の規模や状態によって異なるので一度ご相談ください。 また図面がない場合は筋交いの有無がわからないので、 耐震診断では筋交いがないものとして計算されてしまい、 その結果評点が1.0以下となってしまいます。 それによって耐震改修が必要と判断された場合は耐震改修が必要となります。 しかし、長くその建物を今後も使い続けることを考えているなら たとえ高くついたとしても耐震診断は受けておいたほうが良いです。 対応可能な構造種別
7.応可能な構造種別
鉄筋コンクリート造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・木造、その他
8.耐震診断対応エリア
滋賀県・京都府(その他要相談)
9.所属団体
関西構造設計委員会 社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA)
10.耐震診断補助金制度
滋賀県耐震診断補助金制度はこちらでご確認ください。
11.お気軽にご相談ください
当社には構造設計一級建築士が在籍しております。 耐震診断をご検討中の方や今後耐震診断を検討する可能性のある方も安心してご相談ください。